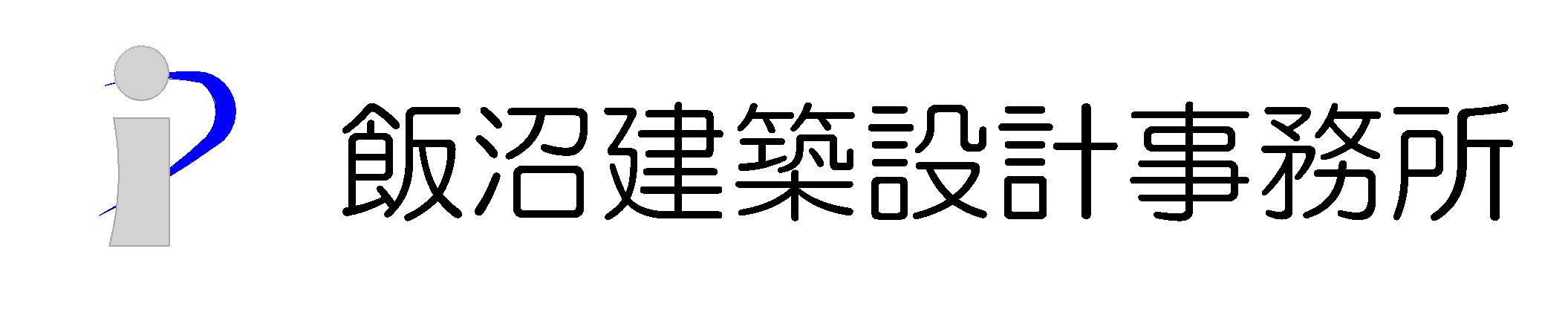傾斜地では敷地を平らにするため、高さが1m~2m程度の擁壁を造る場合があると思います(2mを超えたら確認申請が必要です)
擁壁と言っても、間知ブロック・重力式・L型などがありますが、今回はL型擁壁についてです (L型擁壁は断面がLの字の形をしており鉄筋が入っています)

L型擁壁は立上り部分が傾斜している他の形式と違い敷地の平な部分を広くとることができます。
しかし立ちあがり部分(Lの字の垂直ラインの部分)と底版部分(Lの字の水平ラインの部分)がほぼ同じ寸法になることから、建築主や施工者から、なんでこんなに底版の幅が広いの?とよく言われます。
確かにゴツイしお金もかかります
しかし安全を確保するにはこうなってしまうんです
L型擁壁を造る場合、僕は擁壁構造図集というものから計画に近い高さの構造を参考にしていました。
しかしこの図集は地耐力や土質などの条件が設定されていてますので、条件が異なった場合はそのまま採用できません。また高さが1m・1.5mと区切りの良いものしかないので、1.2mの場合は?となってしまいます
結局構造設計に相談しなければならないことに
そして僕自身は計算していないので、計算上こうなってしまいますとしか説明できないのです
建築主や施工者は納得したようなしないようなさっぱりしない感覚、僕も踏み込んだ説明ができないもどかしさを感じていました
そこでコロナの影響で少々時間ができたので、擁壁計算に挑戦することにしました
久しぶりの構造の勉強に四苦八苦でした
計算をした上での感想ですが、構造図集は条件が同じであれば計算をしてもそれほど変わらず、極端に安全側ではないということ
そして最も影響する条件は地耐力(地盤の耐力)だということ
地耐力不足だと沈下や転倒の項目がいとも簡単にNGになってしまい、底版幅を大きくする必要があり、時には地盤改良を検討しなければなりません(地耐力が十分にあった場合は底版幅を小さくできるのですが、今度は土圧で横に押し出されてしまう(スライド)ということも)
建物部分の地盤耐力調査は当たり前に行われていますが、擁壁がある場合はそちらの調査も重要だと改めて思いました
今後はしっかりした説明ができるかな